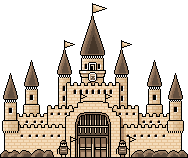<世界文化遺産>
百人一首で有名な慈円は、比叡山について
「世の中に山てふ山は多かれど、山とは比叡の御山をぞいふ」
と比叡山を日本一の山と崇め詠みました。
それは比叡山延暦寺が、世界の平和や平安を祈る寺院として、
さらには国宝的人材育成の学問と修行の道場として、
日本仏教各宗各派の祖師高僧を輩出し、
日本仏教の母山と仰がれているからであります。
また比叡山は、京都と滋賀の県境にあり、
東には「天台薬師の池」と詠われた日本一の琵琶湖を眼下に望み、
西には古都京都の町並を一望できる景勝の地でもあります。
このような美しい自然環境の中で、一千二百年の歴史と伝統が世界に高い評価をうけ、
1994年には、ユネスコ世界文化遺産に登録されました。


<比叡山 延暦寺>
平安時代初期の僧・最澄(767年 - 822年)により開かれた日本天台宗の本山寺院
「延暦寺」とは、比叡山の山内にある500ヘクタールの境内地に点在する約150ほどの堂塔の総称
山内を地域別に、東を「東塔」、西を「西塔」、北を「横川」の三つに区分しています。
これを三塔と言い、それぞれに本堂があります。
<東塔地域>
東塔は、延暦寺発祥の地であり、本堂にあたる根本中堂を中心とする区域
伝教大師最澄が延暦寺を開いた場所であり、
総本堂根本中堂をはじめ各宗各派の宗祖を祀っている大講堂、
先祖回向のお堂である阿弥陀堂など重要な堂宇が集まっています。
|

根本中堂 |
東塔の根本中堂は最大の仏堂であり、
延暦寺の総本堂
現在の姿は徳川家光公の命で
寛永19年(1642)に竣工
 |

大講堂 |
1964年に、山麓坂本の讃仏堂を移築
本尊は大日如来で、その左右には
比叡山で修行した各宗派の宗祖の木像
が祀られています。
|

阿弥陀堂 |
1937年に、建立された、
檀信徒の先祖回向の道場。
法華総持院東塔は、
1980年に阿弥陀堂の横に再興
 |